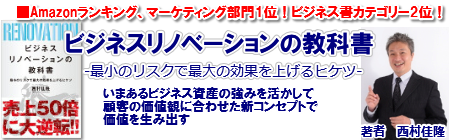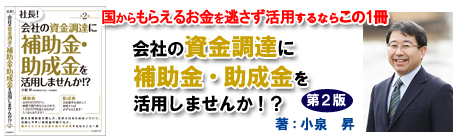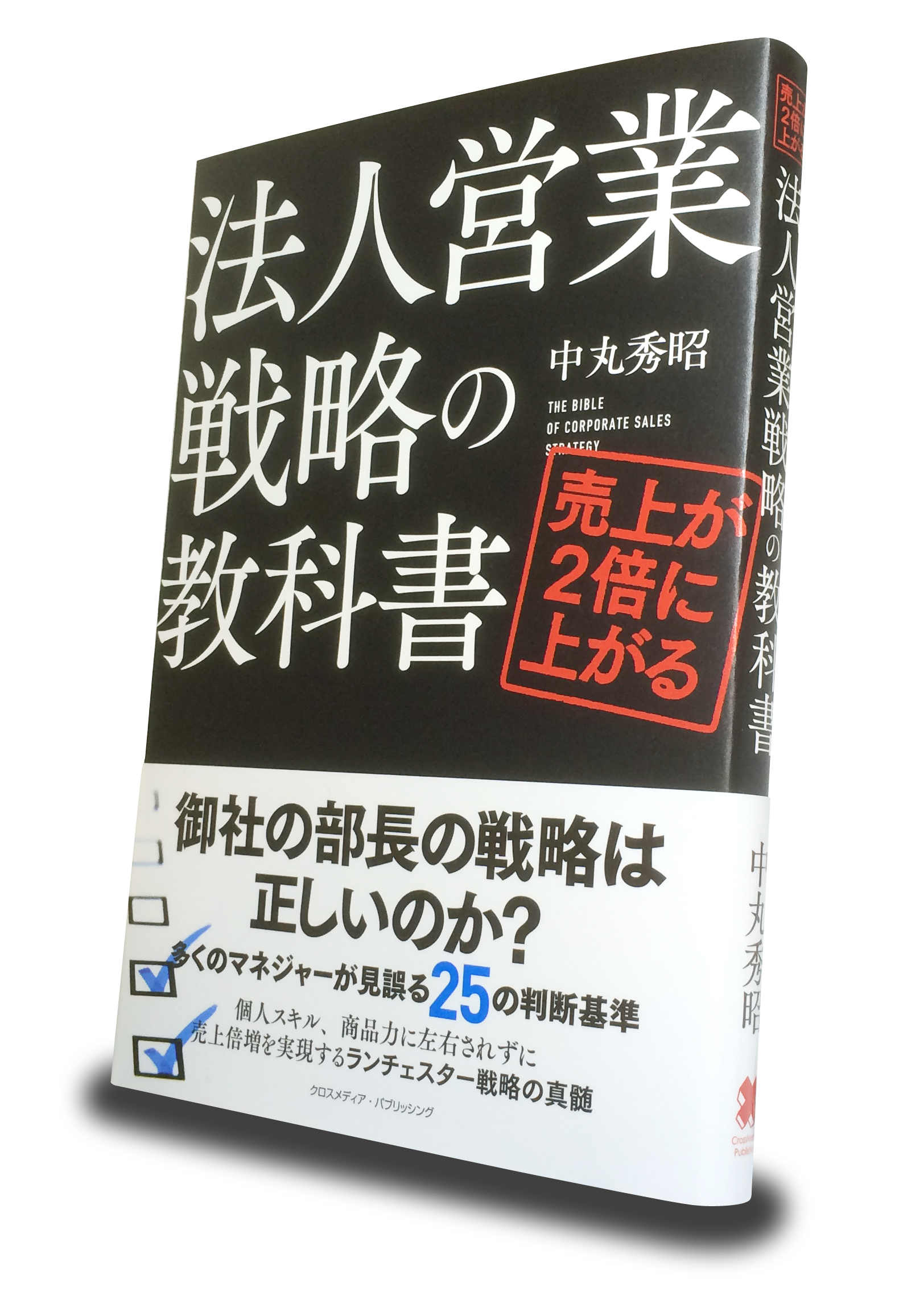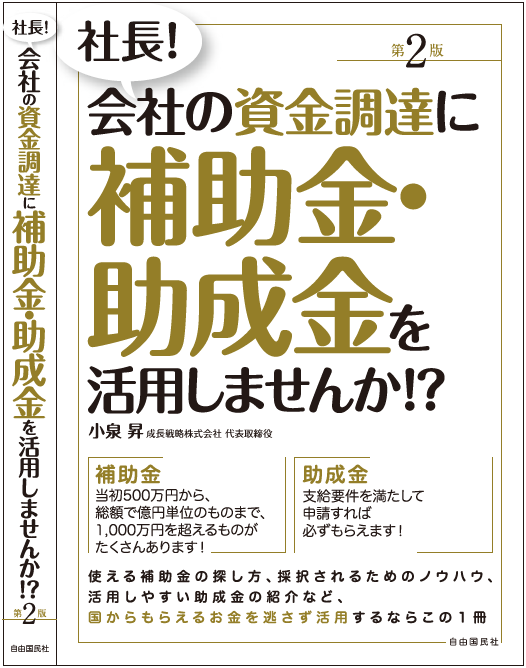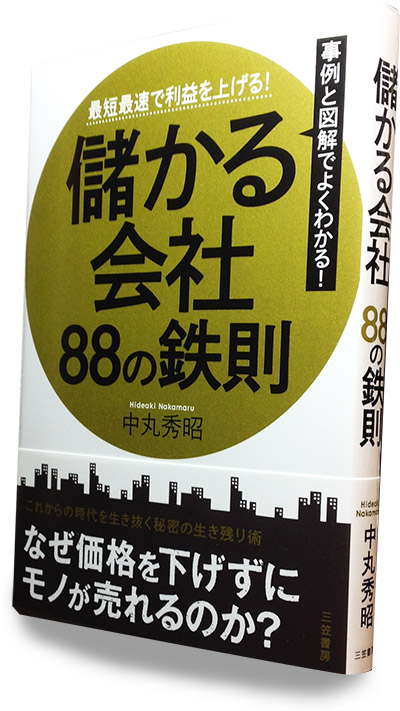「有事のルール ― まとめ/その2」
社会経験も積まず、いきなり法曹のトップポジションに就く、いわば純粋培養の裁判官は、労働者と企業を善悪二元論で図式化して捉える傾向が強いのではないか−とする声があります。もしこれが、そう的外れな言説でないとすれば、こと労働裁判においては、規模の大小を問わず経営側はそれだけでアウェーの立場、つまり相手側にアドヴァンテージが与えられている状況を覚悟して臨まなければならない、ということになります。
正否はさておき、この説が捨て難いのは、これが何も裁判官養成の仕組みだけに問題があるといっているのではなく、根本要因として、日本の構造転換宣言とさえ云われた平成18年5月施行の「会社法」の存在を指摘している処にあります。
判りやすい喩えをひけば、会社法とは、「往来で肩が触れたとき、互いに謝罪し合う」文化、仮に険悪なムードになりそうなときも「第三者が間に割って入って仲裁する」文化から、「自分の非は絶対に認めず、自己主張を繰り返し、相手を非難する」文化、「それぞれの立場を擁護する第三者が、黒白を付けるまで争う」文化=事前調整型社会から事後決着型社会(米国モデル踏襲型訴訟社会)=へと、日本が大きく舵を切ったことを表明する、まさに宣言文そのものだったという事なのです。(日本の訴訟社会化は、とりもなおさず米国の保険会社にとって垂涎の好機。会社法は、明らかに米国の圧力に屈した結果であり、司法制度改革も保険参入と対をなすその為の露払いに他ならない−とする考え方と一致します)
皮肉なことに、訴訟社会の本場米国では「日本の謝罪文化に学ぶべきではないか」という声が日に日に高まっている、とも云われる中で、近頃の日本では、事前調整の過程を経ることも無く、いきなり争いの場が用意されてしまう、という状況が増加しています。
会社法と歩調を合わせたかのような労働審判の法制化(平成18年)やWEBによる情報収集の易化・共有化も、こうした事態を加速させる要因であり、遺憾ながら「平時の有事化」は止めようがないのが実情ですが、それでも対策を講じる必要があるとすれば、どのようなものがあるでしょうか。
この場合、前号でご紹介した、多くの弁護士を擁し最高裁まで争い続けようという大手企業の有り様は、いわば全くの例外であり、「経営側一般」としてモデル化するには相応しくありません。
その一方、大資本に長期にわたり立ち向かい続ける一人の労働者という図柄も又、正鵠を射ているとは云い難いものがあります。
そのバックには、話題性が高く、耳目を集めるケースであればある程、大企業に勝利したという相応の成果(宣伝効果)が期待できるユニオンの支援があることが少なくないからです。
云うまでも無く、紛争を力づくで捻じ伏せようとすれば、それ相応の反発があるのは必定であり、解決が遠のくばかりか費用も嵩み、凡そ中小企業向きとは申せません。
勝ちにこだわり、和解勧告に応じず、その挙句敗訴となれば、測り知れない精神的ダメージに加え、事案によっては付加金(労基法114条。労働者に対する未払い金が認定された場合、それと同額が課される一種の罰金で、これが命じられた場合、いわゆる‘倍返し‘になり、たとえば元々の未払い金が300万だとすると、計600万の支払い義務を課されることになる訳です)と利息(和解では不要)も払う羽目になります。
無論、金融機関がこのような後ろ向きの資金を用立てるはずも無く、却って融資引き上げの口実となる恐れさえあるといっても過言ではありません。
上告はおろか控訴すら論外、第一審の敗訴も回避が至上命題であるというのは、このような背景があるからなのであり、一労働者を間に挟んだ、大資本とユニオンとの面子を掛けた争いは、中小企業にとっては迷惑至極な話でしかないのです。
こうした無益な争いの種を、少しでも取り除いておくため、次号では、組織体制が整っていなくとも可能な、転ばぬ先の杖となり得る具体的対策をご紹介する処から始めたいと思います。
「有事のルール ― まとめ/その2」
著者/